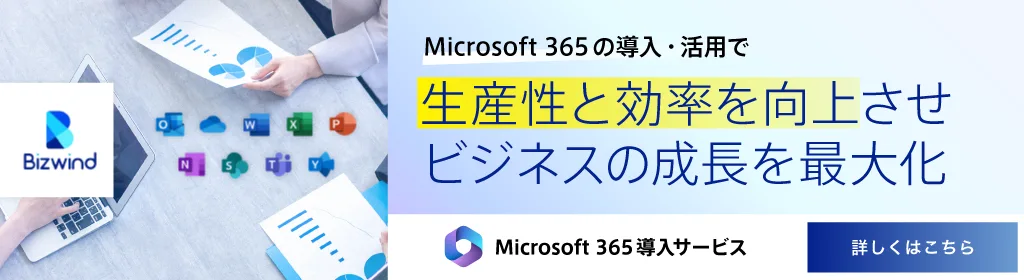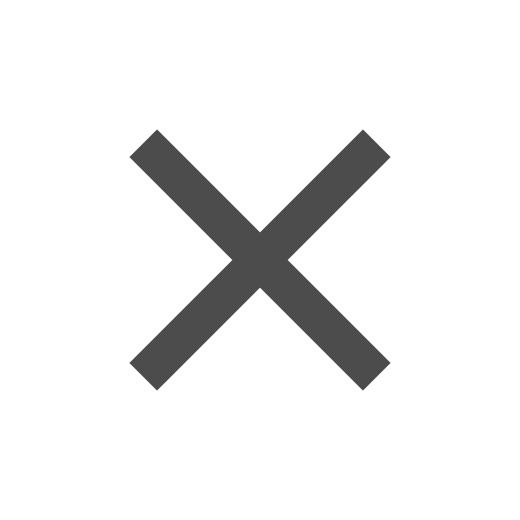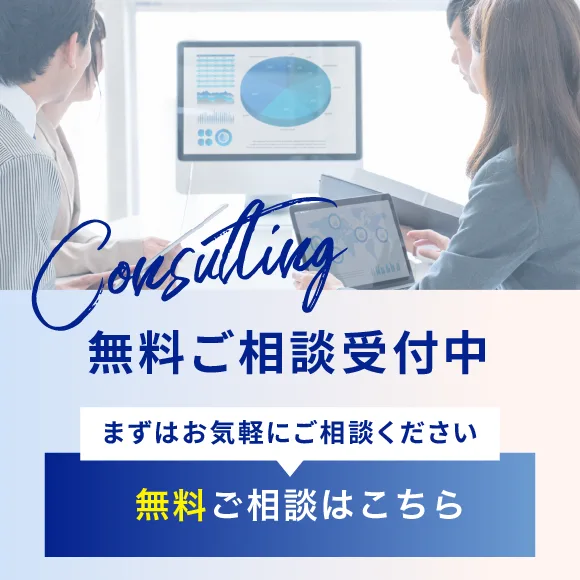記事の監修
S.Sato
記事の監修
S.Sato
マネジメント&イノベーション事業部 開発部/2グループ グループマネージャー
資格:Microsoft Offiece Specialist Master 2007、ITパスポートなど
2022年よりMicrosoft365とPowerPlatformの案件を担当。
それ以前は業務・Web系システムを要件定義からリリースまでの開発に従事。
IT業界歴15年の経験を活かし、PJを牽引し後続の育成にも力を注ぐ。
趣味は散歩で、思考が煮詰まった際には、近所の緑道を散歩し、新たな発見や自然からのインスピレーションを受けている。
この記事では、デジタルトランスフォーメーションが求められている背景や具体的な進め方、注意点などについて解説します。
Contents
目次
デジタルトランスフォーメーションが求められている背景

なぜ今デジタルトランスフォーメーションが求められているのでしょうか。まずは、その背景を探っていきましょう。
スマホやデジタル化による消費行動の変化
一つ目の理由は、スマホや情報のデジタル化により、顧客の消費行動に変化が生じた点が挙げられます。インターネットやEコマースがなかった時代、顧客は店舗やサービス提供者の元に直接おもむき、そこで商品情報を得て購買の判断を行っていました。商品の情報は提供者からもたらされることが多かったため、多角的な視点を持つことが難しかったといえるでしょう。
一方、現代はインターネットやスマホの登場により、消費者は自分の欲しい商品やサービスについて多くの情報を得ることができるようになりました。メーカーからもたらされるものはもちろん、実際に商品を購入して使ってみた人の感想や識者のレビューなど、大量かつ多角的な情報を得てから購買判断を行っています。
そのような市場においては、より消費者のニーズに合わせたきめ細やかな商品やサービスを提供することが求められます。デジタルトランスフォーメーションにより顧客のニーズを深く把握し、その一助とするわけです。
働き方改革やテレワークの推進
働き方改革による労働時間の短縮、またテレワークの推進などによってもデジタルトランスフォーメーションが求められています。労働時間を短縮するからといって売上や利益まで下げるわけにはいかないため、より少ないリソースで大きな結果を出さなければなりません。
また、テレワークを行うにあたっても業務のデジタル化が必須です。従来のオフィスワークであれば書類や資料を紙ベースで管理することも顔と顔を合わせたコミュニケーションを行うこともできましたが、テレワークにおいてはデジタル化された資料やコミュニケーションをうまく活用していく必要があります。
事業への持続性や再現性の要求
最後に挙げられるのは、事業への持続性および再現性の要求です。「持続性」という言葉はトレンドワードでもありますが、意味としては「長持ちする」「長期的な視点がある」になるでしょう。
持続性のある事業とは、「長期的な視点から構築されている長持ちする事業」のことです。ビジネスで利益を産む方法は数多くありますが、中には短期的にしか効果の出ないものもあれば、短期では効果は見込めないものの長期的な期待値が大きいものもあります。
そういった持続性の高い事業、そして成功確率の高い再現性のある事業スタイルを構築するために、デジタルトランスフォーメーションが求められています。
従来のIT化とデジタルトランスフォーメーションの違い
では、次に従来のIT化とデジタルトランスフォーメーションの違いについて解説します。両者はよく似た言葉ですが、一体どのような違いがあるのでしょうか。
IT化はデジタル機器を活用し業務を効率化することに重点が置かれていた
基本的に、IT化という言葉は「デジタル機器を用いて業務効率化を促すこと」と定義されることが多いのではないでしょうか。主体はあくまでデジタル機器であって、それらがもたらすさまざまな効果により業務効率化を進めようといった取り組みです。
効果測定はもちろん行われるものの、どちらかというとIT機器の導入が主目的となりがちです。IT機器導入による効果データがあまり出揃ってない時代にスタートしたためでもあるでしょう。
デジタルトランスフォーメーションはIT機器を導入して終わりではない
デジタルトランスフォーメーションにおいてもIT活用を行うことは変わりませんが、IT化と比較すると、より効果や生産性に重きが置かれた概念です。そもそもデジタルトランスフォーメーションという言葉は、経済産業省のガイドラインにより下記のように定義されています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
参考:https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf
デジタル技術を活用して得られるものは、業務の効率化にとどまりません。たとえば、「顧客にまつわるさまざまなデータを収集・分析して新商品の開発やマーケティングに役立てる」「従業員から収集したナレッジを蓄積して成功の再現性を高める」なども含まれるでしょう。
企業の数だけデジタルトランスフォーメーションがある
IT化という言葉がIT機器の導入という分かりやすい事象を指すのに対し、デジタルトランスフォーメーションという言葉の具体的意味は多岐に渡ります。ある企業にとっては販売戦略策定のためのIT基盤構築をデジタルトランスフォーメーションと位置づけたり、またある企業では異なる分野や手法がそれに該当するケースもあるでしょう。
そのため、企業の数だけデジタルトランスフォーメーションが存在するといっても過言ではありません。明確な定義を求めすぎると逆に分かりづらくなって施策が進まない可能性もありますので、柔軟に捉えておくことをおすすめします。
デジタルトランスフォーメーションのメリット

では、続いてデジタルトランスフォーメーションのメリットをご紹介します。デジタルトランスフォーメーションを推進することで、どのような恩恵があるのでしょうか。
競争力が増す
適切なデジタルトランスフォーメーションを進めることができれば、企業の競争力強化に繋がります。デジタルトランスフォーメーションに取り組めば、従来よりさらに詳細な情報やデータを得ることができるでしょう。
それらを元に販売戦略策定や新商品開発を行えば、成果が上がりやすくなります。また、客観的な指標を多く得ることができるため、キーマンの説得にも役立つでしょう。
結果として事業の成約性やスピードが上がり、競争力強化が見込めます。
データや知見が蓄積される
デジタルトランスフォーメーションの進め方にもよりますが、さまざまなデータや知見が蓄積されていくこともメリットとして挙げられます。従来は顧客の大まかな行動や事業のざっくりとした進め方などを記録して蓄積していましたが、より細かな部分は現場や担当者の勘に頼るところも大きかったのではないでしょうか。
デジタルトランスフォーメーションを推進すれば、ITテクノロジーを駆使して細かなデータや知見を収集し積み重ねることが可能です。それらを元に事業戦略を考えたり組織運営を行うことで、直感に頼らない客観性を重視した経営スタイルを構築できるでしょう。
事業に再現性をもたせることができる
デジタルトランスフォーメーションのメリットとして、事業に再現性をもたせられるというものも挙げられます。再現性をもたせられるとは、たとえば社内でA事業を行い成功したノウハウをB事業に適用することで、より成功確率を高められるというイメージです。
もちろん100%というわけにはいきませんが、まったくの白紙状態から行うよりは成功のための指針を得られるでしょう。デジタルトランスフォーメーションを適切に進めていればA事業を行った際のデータや市場の反応がシステムにしっかりと蓄積されているはずなので、それを参考にB事業を構築することができます。
デジタルトランスフォーメーションの具体的な進め方
では、どのようにデジタルトランスフォーメーションを推進すればよいのでしょうか。続いて、デジタルトランスフォーメーションの具体的な進め方をご紹介します。
トップダウンで戦略を策定する
デジタルトランスフォーメーションを進める際に大事なのは、原則的にトップダウンで行うことです。デジタルトランスフォーメーションをどのように定義するかにもよりますが、全社的かつ中長期的なプロジェクトになることも多いため、単一部署や担当者のみに任せるのは負担が大きくなってしまいます。
ここで大事なのは、経営トップのデジタルに対する理解をしっかりと深めておくことです。デジタル領域への理解が薄いと指示が曖昧になってしまい、現場を混乱させデジタルトランスフォーメーションの進行に支障をきたしてしまう恐れがあります。
現状の課題を分析する
多くの会社が既にIT機器を導入しビジネスを行っているかとは思いますが、一度それらがどのように使われているかを精査しましょう。どの部分が老朽化しているのか、データは一元管理されているのか、システムの連携に問題はないか、などのポイントを確認します。
その上で、導入されているシステムをどのように定義しなおすか、そして何を廃棄し何を新しくするかなどを判断します。もちろん、場合によってはシステムの入替えが必要ないケースや、全てを刷新するようなケースもあるでしょう。
業務のデジタル化を行い運用する
システムの導入やワークフローの策定が完了したら、業務のデジタル化を進めます。まずは既存の事業をデジタルテクノロジーにより高度化し、それに沿ったワークフローを構築運用します。
既存業務でデジタル化における十分な知見を蓄えることができれば、それを新規事業に活かすこともできるようになります。一度業務のデジタル化を行えば、二度目三度目はより負荷を逓減させ移行させることも可能でしょう。
デジタルトランスフォーメーションを進める際の注意点

それでは、最後にデジタルトランスフォーメーションを進める際の注意点について解説します。
目的や課題を明確にする
デジタルトランスフォーメーションを取り入れるにあたり、「何のために行うのか」「どのような課題を解決したいのか」を明確にしておくことが大事です。デジタルトランスフォーメーションを推進するのは当然ながらそれ自体が目的ではなく、業務効率化や生産性の向上、また何かしらの問題を解決するために行うものです。
目的や課題が不明確なままだと、具体的なロードマップを描くことができません。指針が定まってないのに手だけを動かしても成果に繋がることは少なく、現場の疲弊を招くだけの結果となってしまいます。
デジタルトランスフォーメーション自体は単なる一つの手法に過ぎませんので、それを取り入れて何がしたいのか?という部分が重要です。
変革を恐れない
デジタルトランスフォーメーションを推進することにより、今まで使っていたシステムやワークフローの変化が起こります。何がどの程度変わるのかは各々異なりますが、変化させることで逆に生産性が下がったり、現場から不満の声があがる恐れもあります。
だからといって、変革を恐れていては時代に遅れをとるだけでしょう。挑戦には失敗がつきものであり、失敗体験を活かすことでより成功に近づけるというのが事業経営における一般的な法則です。
大事なのは、「変革を恐れない」ことと「失敗から学ぶ」ことです。誰しも失敗は嫌なものであり、手掛けていた事業やプロジェクトの結果が芳しくない場合、チームにネガティブな空気が蔓延します。
だからこそ、それを糧にしなければなりません。
自社に合った手法を模索する
デジタルトランスフォーメーションの一般的なやり方としては、業務のデジタル化を行いそこから得られたデータや知見を事業に活かす形になります。そのため業務のデジタル化が必須になるのですが、デジタル化することが必ずしも生産性向上と結びつかないケースもあるでしょう。
そのような場合は、一旦デジタルトランスフォーメーションを脇に置いて、自社にとってのベストを模索することをおすすめします。デジタルトランスフォーメーションはそれ自体が目的というわけではなく、デジタル化による業務効率化や生産性の向上が主目的です。
逆に生産性を阻害してしまう結果が見えているのであれば、敢えてデジタルトランスフォーメーションを行わないという選択肢も生まれるのではないでしょうか。もちろん、多くの場合はデジタル化による生産性への寄与は無視できないものがあります。
デジタルトランスフォーメーションを諦めるにせよ、その決断には十分な熟考および検証が必要です。もしかしたら、具体的手法や選んだシステムが悪かっただけかもしれません。
まとめ
デジタルトランスフォーメーションが求められている背景には、生産性向上やテレワーク推進、事業の持続性確保などがあります。自社にとって適切なデジタルトランスフォーメーションの進め方を模索し、業務の効率的なデジタル化を目指しましょう。

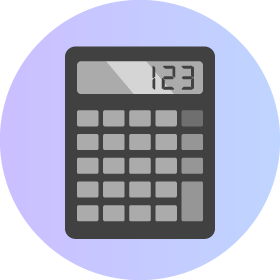
Microsoftを導入して
コスト効率をよくしたい

Microsoftに関して
気軽に聞ける相談相手が欲しい

Microsoftを導入したが、うまく活用できていない・浸透していない

社内研修を行いたいが
社内に適任者がいない
Bizwindでは、Microsoft導入支援事業などを中心に
IT・DX推進に関する様々なご相談を承っております。
ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。