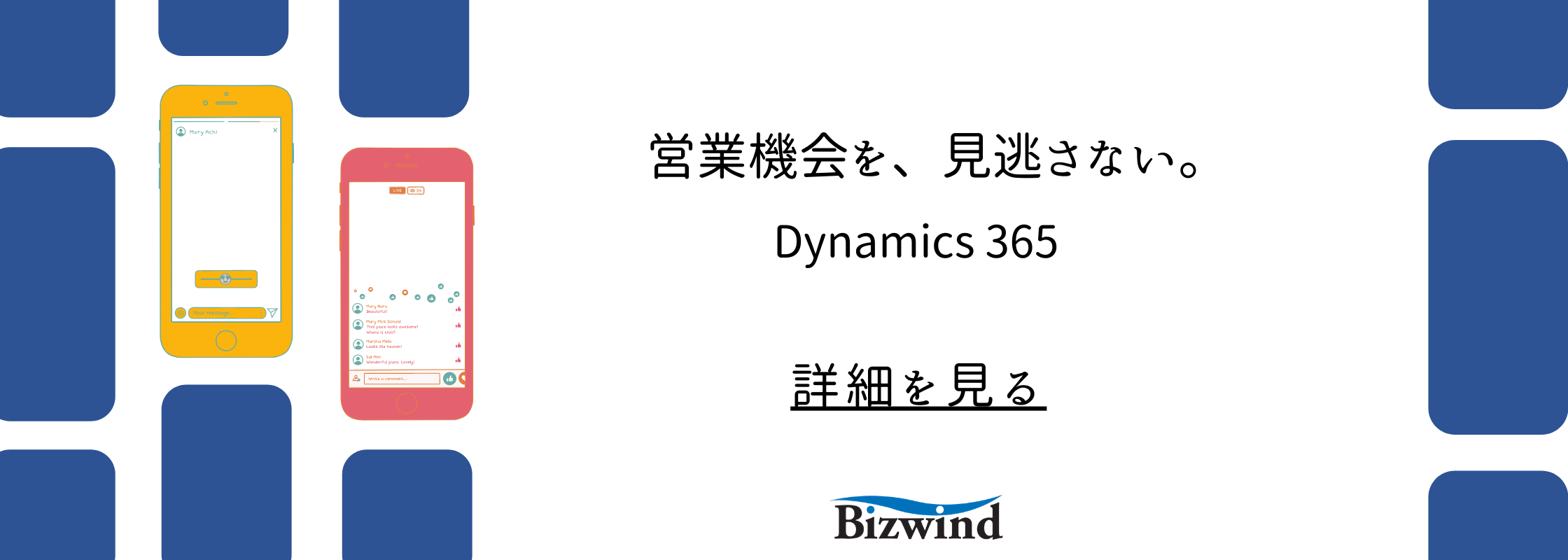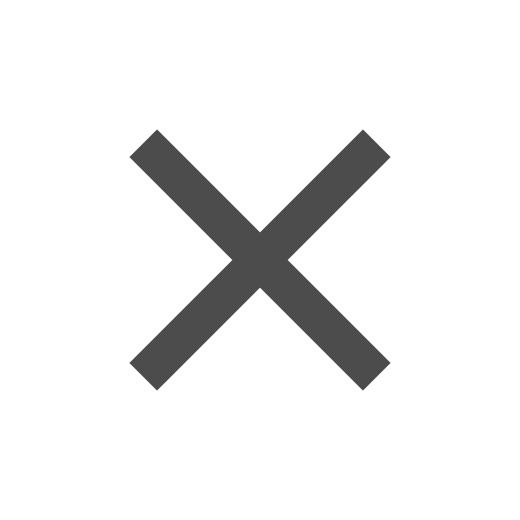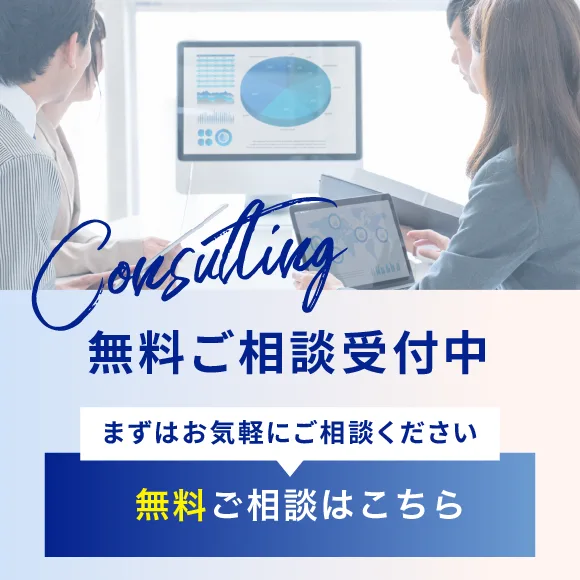記事の監修
S.Sato
記事の監修
S.Sato
マネジメント&イノベーション事業部 開発部/2グループ グループマネージャー
資格:Microsoft Offiece Specialist Master 2007、ITパスポートなど
2022年よりMicrosoft365とPowerPlatformの案件を担当。
それ以前は業務・Web系システムを要件定義からリリースまでの開発に従事。
IT業界歴15年の経験を活かし、PJを牽引し後続の育成にも力を注ぐ。
趣味は散歩で、思考が煮詰まった際には、近所の緑道を散歩し、新たな発見や自然からのインスピレーションを受けている。
Contents
目次
インサイドセールスとは何か

インサイドセールスとは、どのような概念なのでしょうか。従来のセールスとは何が異なるのでしょうか。
まずは、インサイドセールスの基礎知識について解説します。
顧客先に出向かず、電話やメールといった遠隔的なコミュニケーションを行う営業スタイル
インサイドセールスとは、顧客先を訪問せず電話やメールといった遠隔的なコミュニケーションを用いて行う営業スタイルのことです。従来は、顧客先を直接訪問しプレゼンや商談を行い契約を結ぶという営業スタイルが一般的でした。
現在でも、そのやり方で成果を上げている企業はいくつもあります。やはり直接会って話をして商品やサービスの特性を知りたい、営業マンや会社の人となりを知りたいといったニーズは普遍なのでしょう。
しかし、そのやり方では立ち行かなくなってきた企業や業種も存在します。そこで生まれたのが、より効率性を重視したインサイドセールスというわけです。
国土が広く訪問に時間がかかるアメリカで発祥
インサイドセールスは、国土が広く顧客訪問に時間のかかるアメリカで発祥しました。従来の顧客訪問型セールスは相手に安心感を与えられる一方、顧客先まで出向く時間や交通費といったコストが発生します。
アメリカのような広い国土を持つ国では、そのコストを無視するのは難しかったのでしょう。電話やメールであれば、かかるコストは通信費が大半です。加えて、営業マンの時間も節約できるため、日に何件もアポイントを入れることができます。
業種や企業の特性にもよりますが、ニーズが上手く合致すれば費用対効果の高い営業活動を行えるでしょう。
インサイドセールスを行うメリット
それでは、次にインサイドセールスのメリットをご紹介します。インサイドセールスを行うことで、一般的に下記のような利点が生じます。
顧客とのコミュニケーションが効率化される
インサイドセールスにより、顧客とのコミュニケーションを効率化できます。インサイドセールスの主なコミュニケーション手段は電話やメール、その他オンライン通信になりますので、相手先を訪問する必要がありません。
オフィスに在籍したまま顧客とのコミュニケーションを行うことができるため、時間を有効に使えます。また、メール等文章によるやり取りを活用することで伝達ミスや確認ミスを防ぎ、同じことを何度も繰り返す手間を省けます。
加えて、「言った言わない」のような水掛け論を防ぐ効果も見込めるでしょう。
コスト節約に繋がる
インサイドセールスを活用することで、コストの節約に繋がります。相手先を直接訪問する場合は交通費や資料代など、さまざまなコストがかかります。
インサイドセールスを行いコミュニケーションの効率化を図ることで、それらのコストを削減することができるでしょう。相手先を訪問する必要がないので交通費はかかりませんし、直接会うわけでもないので諸々の雑費もかかりません。
また、資料はデジタル化して送付すればいいため、印刷代や紙代を節約することもできます。そして何より、時間あたりの生産量が増えるため、営業マンの人的コスト削減にも繋がります。
営業マン個人でなくチームで顧客対応ができる
従来の営業スタイルでは、各顧客を担当する営業マン個人が対応を行うのが一般的でした。もちろんメリットもありますが「営業マン個人に顧客情報が集約される」というデメリットも生じていたのではないでしょうか。
そうなると、担当営業マンがいないと満足な顧客対応ができなくなってしまいます。きめ細やかでニーズに沿った対応ができない場合、顧客満足度が下がってしまう恐れもあるでしょう。
インサイドセールスに切り替えることで、営業マン個人でなくチームで顧客対応ができるようになります。インサイドセールスは相手先を訪問するのではなくオフィスから営業活動を行うため、情報が社内に集約されることになります。
社内に集約された情報を元に対応する形になるため、誰がやっても一定水準の顧客対応が可能になるわけです。
インサイドセールスに役立つツールをご紹介

では次に、インサイドセールスに役立つツールをいくつかご紹介します。インサイドセールスを行うにあたっては対応したシステムやツールが必須と言えるでしょう。
CRM
CRMには、下記のような機能が搭載されています
- 顧客管理機能
- 分析機能
- プロモーション管理機能
顧客管理機能では、顧客の名称や所在地、購買情報などを記録し管理することが可能です。分析機能では、顧客データベースを元に多角的な分析を行い、マーケティングなどに活かすことができます。
プロモーション管理では、顧客をさまざまな条件で抽出し、ターゲットに沿った販売施策を行えます。
SFA
SFAはSales Force Automationの略であり、日本語では「営業支援システム」と呼ばれています。営業活動におけるプロセスを管理し、営業生産性の向上に寄与するためのシステムです。
SFAには、主に下記のような機能が備わっています。
- 案件管理機能
- 営業活動管理機能
- 売上予測・予実管理機能
案件管理機能は、各顧客に対する営業活動の過程や情報を管理する機能です。主に管理者のための機能であり、記録されている案件管理情報に基づいて各担当者にアドバイスを出せるというメリットがあります。
営業活動管理は、各営業担当社の実績を管理し、評価やフィードバックに繋げるための機能です。売上予測や予実管理は、現在の情報に基づいて売上を予測したり、予実管理を行うための機能です。
MA
MAはMarketing Automationの略であり、日本語でもそのまま「マーケティングオートメーション」と呼ばれています。マーケティングの各プロセスを自動化し、効率的なマーケティングを行うためのシステムです。
マーケティングオートメーションには、下記のような機能が搭載されています。
- メルマガ配信機能
- メディア作成機能
- スコアリング機能
メルマガ配信機能では、ターゲットニーズに沿ったメールマがジンを送付し、購買意欲の啓蒙に役立ちます。メディア作成機能では自社のオウンドメディアなどを作成し、リード獲得などの効果が見込めるでしょう。
スコアリングでは、獲得したリードをスコアリングし、購買熱量を図ります。十分にホットになったリードを営業担当者に渡すことで、成約率を高めることができます。
オンライン会議システム
テレワークでお馴染みのオンライン会議システムも、インサイドセールスの強い味方でしょう。遠隔コミュニケーションとしては電話やメールも有力ですが、オンライン会議システムであればそれらを凌ぐ密なコミュニケーションが可能です。
音声+映像を用いることで、距離は離れていても顧客および担当者の距離感を縮めることができます。加えて、資料を即共有できたり疑問点をその場で解消できるなど、営業活動を効率的に進めるための工夫も構築できるでしょう。
自社に合うツールをどのように見極めるか
自社に合うツールはどのように見極めればよいのでしょうか。続いて、ツールを正しく選ぶための手法を解説します。
自社がどのようにインサイドセールスを行うかを明確にする
まず大事なのは「自社にとっての『インサイドセールス』を明確に定義する」ことです。インサイドセールスは前述の通り「遠隔的なコミュニケーションを用い営業活動を行う」ことですが、これをさらに深堀りする必要性があるでしょう。
具体的には、下記のような項目の検討が挙げられます。
- 100%インサイドセールスにするのか、それとも場合によっては相手先を訪問するのか
- コミュニケーション手段はどうするか
- 営業担当者の評価はどのように行うか
不確定な部分を残せば残すほど、ツール選びのニーズが曖昧になります。曖昧なニーズのまま製品選びを行うと、後から「こんなはずじゃなかった」ということになりかねません。
自社のインサイドセールスに対する定義を明確にし、ニーズを正しく設定しましょう。
そのニーズを満たしてくれるツールを検討する
インサイドセールスに求めるものが明確になったら、それを指針にツール選びを行います。ニーズが明確化されていれば自ずと必要な機能も絞り込めているはずなので、それが搭載されているツールを探します。
ツールにはそれぞれ特徴があるため、自社が強く求めるものとツールの強みを合致させるようにしましょう。そこが一致していないと、ツールの強みを存分に発揮できないかもしれません。
プロに相談するのも手
ツール選びが難航するようであれば、プロに相談するのも手です。ITシステムやツールのプロであれば、個別の製品に関する知見が豊富なため、自社にとってより良い選択肢を提案してくれるでしょう。
また、実際にツールを導入した事例から、効率的な運用アドバイスをもらえるかもしれません。ツールは正しく活用してこそ意味が生じます。導入前の注意点や導入後の運用サポートなどを得られれば、活用をスムーズに進められるでしょう。
成果を上げるためのツール活用ポイント

では、最後に成果を上げるためのツール活用ポイントについて解説します。どのような方法論を用いれば、ツールの価値を最大限発揮できるのでしょうか。
ツールは使われてこそ意味をなす。機能も大事だが使い勝手や操作感も大事
ツールは使われてこそ意味のあるものです。誤ったツールを導入した結果現場で使われず、埃を被るような事態は避けなければなりません。
そのために大事なのは、使い勝手や操作感です。搭載機能ももちろん大事なのですが、機能の選択はツール選びの段階で完了しているはずなので、現場としては「とっつきやすさ」が重視されることになるでしょう。
いくら機能的に問題ないとはいえ、使い勝手の悪いツールは敬遠されてしまいます。初めて触る人でも直感的に使えるような、ユーザビリティの高いツールを選びましょう。
利便性とセキュリティを天秤にかける
ツールの選定や活用には、利便性とセキュリティの両輪が必要です。利便性が欠けたら生産性が落ち、何のためにツールを導入したかが分からなくなってしまいます。
対して、セキュリティに問題が生じた場合は情報漏えいなどのリスクに晒されることになるでしょう。どちらもツールを十分に活用するためにはなくてはならない要素なので、両者を天秤にかけ、良いバランスを保つ必要があります。
セキュリティに関しては、ツール単体でなくネットワーク全体で対処することも求められます。ネットワークや基幹システム全体から見て、セキュリティリスクの生じないツールの選定や活用が大事です。
ツールに頼りすぎないことも大事
最後にお伝えしたいのは、ツールに頼りすぎないことも大事であるという点です。ツールは非常に便利なものですが、ツールを活用するために業務内容を変化させるのは、場合によっては本末転倒になります。
ツールは、あくまでも業務の生産性を向上させるためのものです。導入時に一時的に下がるようなケースはあるかもしれませんが、長期的に生産性が上がってこない場合は問題でしょう。
その場合は、ツールの活用もしくは選定を誤っている可能性があります。そういったケースにおいては(極論かもしれませんが)「ツールを使わない」という選択肢も視野に入ります。
目的は、あくまで「生産性の向上」です。ツールはそのための手法の一つに過ぎませんので、明確に目的を阻害する場合はワークフローから除外するのもよいかもしれません。
まとめ
インサイドセールスを行うことで、客先を訪問せずとも営業活動に励むことができます。自社に合ったインサイドセールスのためのツールを見極め、営業活動の生産性を向上させましょう。

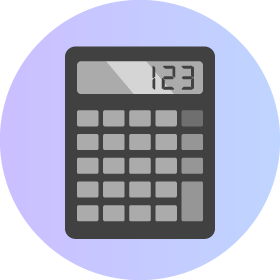
Microsoftを導入して
コスト効率をよくしたい

Microsoftに関して
気軽に聞ける相談相手が欲しい

Microsoftを導入したが、うまく活用できていない・浸透していない

社内研修を行いたいが
社内に適任者がいない
Bizwindでは、Microsoft導入支援事業などを中心に
IT・DX推進に関する様々なご相談を承っております。
ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。