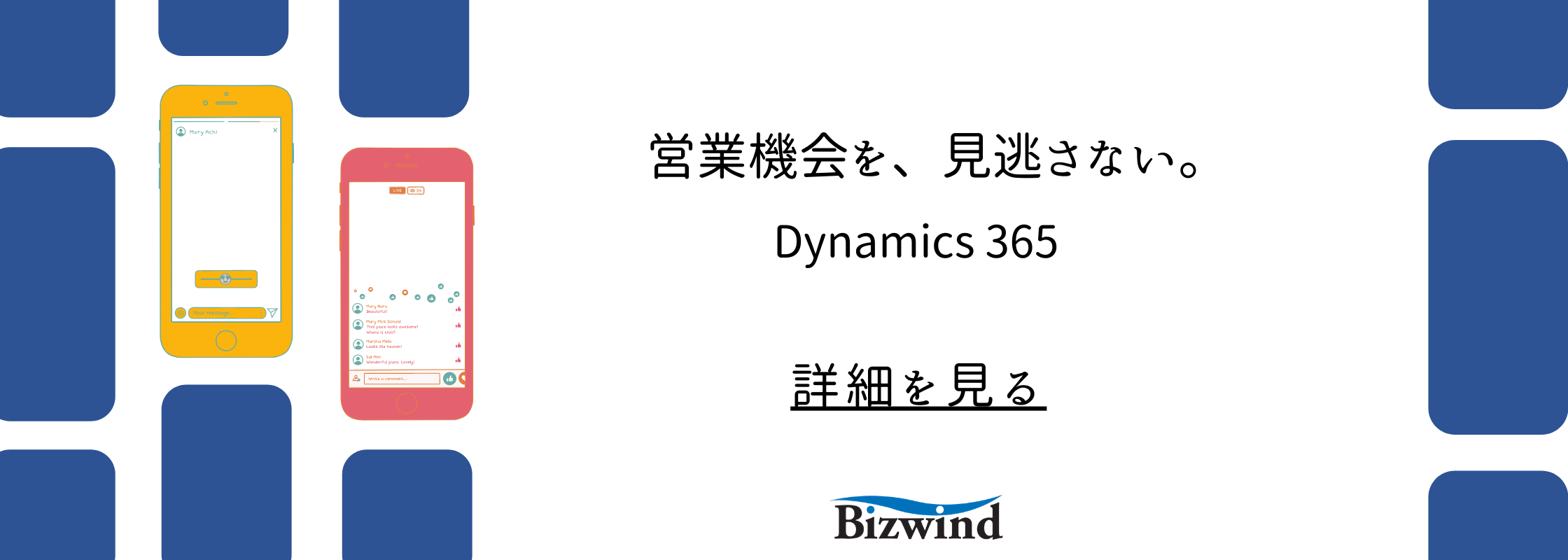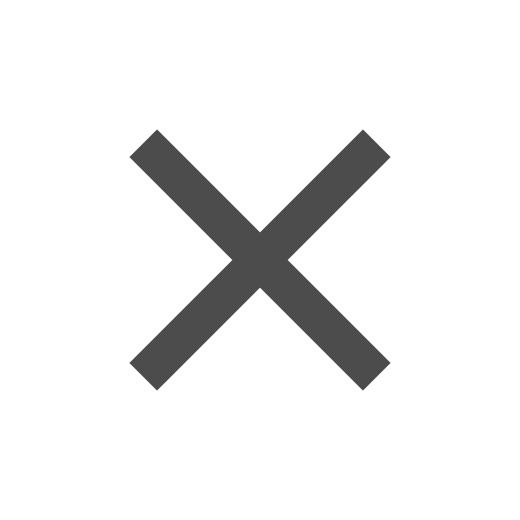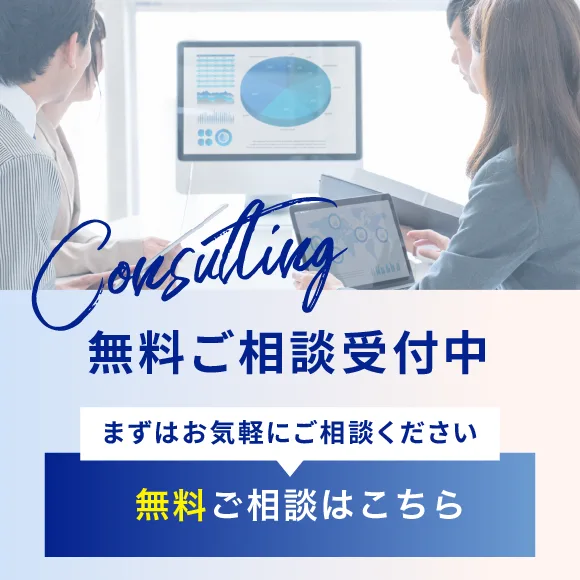記事の監修
S.Sato
記事の監修
S.Sato
マネジメント&イノベーション事業部 開発部/2グループ グループマネージャー
資格:Microsoft Offiece Specialist Master 2007、ITパスポートなど
2022年よりMicrosoft365とPowerPlatformの案件を担当。
それ以前は業務・Web系システムを要件定義からリリースまでの開発に従事。
IT業界歴15年の経験を活かし、PJを牽引し後続の育成にも力を注ぐ。
趣味は散歩で、思考が煮詰まった際には、近所の緑道を散歩し、新たな発見や自然からのインスピレーションを受けている。
この記事では、会社にまつわる利益の種類、利益を上げるための方法、そのためのシステムについて解説します。
Contents
目次
会社の「利益」には次のようなものがある
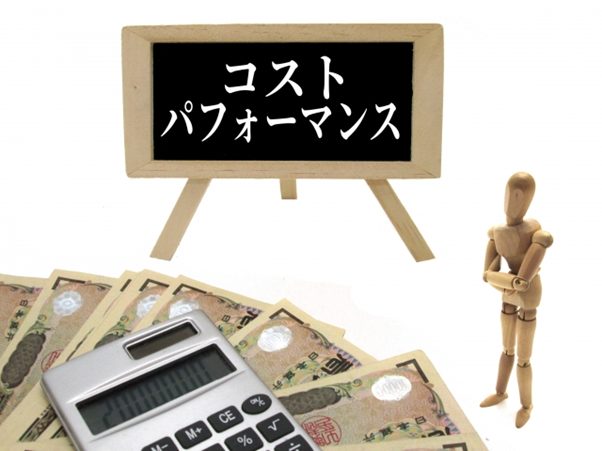
会社の利益には、主に次のようなものがあります。
売上総利益(粗利)
一つ目は、「売上総利益」です。粗利と呼ばれることも多い売上総利益は、売上高から売上原価を差し引いたものです。
売上高は会社が自社製品などを販売して得た収入のことであり、売上原価は売れた商品の製造にかかった費用のことです。すなわち、売上総利益とは「本業から得られた利益」になります。「(自社が行っている事業の)付加価値の大きさ」とも言い換えられるでしょう。
なお、製造業の場合は売上原価ではなく、製造原価が用いられます。
営業利益
会社にまつわる利益としては、「営業利益」も挙げられるでしょう。営業利益は、上述した売上総利益から「販売費および一般管理費(販管費)」を差し引いて算出されます。
販管費とは、自社商品を販売するためにかかった費用や会社を運営するためにかかる一般的な費用のことです。たとえば、下記のようなものが挙げられるでしょう。
- 広告宣伝費
- 給与・賞与
- 光熱費
- 消耗品費
すなわち、営業利益とは「本業で稼いだ利益」のことです。
経常利益
次に挙げられるのは、「経常利益」です。経常利益は営業利益に営業外収益を加算し、営業外費用を差し引くことで求められます。
営業利益は前述の通りです。営業外収益とは本業以外から得られた収益であり、営業外費用は本業以外にかかった費用のことです。
例としては、下記のようなものが挙げられるでしょう。
- 貸付金利息(収益)
- 保有株式の配当(収益)
- 借入金利息(費用)
- 社債の利息(費用)
経常利益は、「会社が本業・本業以外を含めた事業全体から経常的に得た利益」となります。
税引前当期純利益
会社にまつわる利益には、「税引前純当期利益」というものもあります。税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を加え特別損失を差し引くことで求められます。
特別利益(損失)とは、臨時に起きた出来事から得られた利益(損失)のことです。たとえば、下記のようなものが挙げられます。
- 保有不動産の売却
- 臨時的な固定資産の廃棄
- 災害による損失
税引前当期純利益は、会社の企業活動から得られた最終的な利益に近い数字です。原則的に、税金を支払う場合は税引前当期純利益を原資とします。
当期純利益
最後に挙げられるのは、「当期純利益」です。当期純利益は、税引前当期純利益から法人税などの租税を差し引いた利益です。
当期純利益は企業が得た収益から税金を支払い、最終的に社内に留保される額と言えるでしょう。
利益を上げるにはどうするか
では次に、利益を上げるための方法について解説します。
売上を上げる
一つ目の方法は、売上を上げることです。前述の通り、利益というのは「売上ー費用」でざっくり計算できるため、大元である売上を高めることで利益も上がります。
売上を上げるには、下記のようなやり方が考えられるでしょう。
値上げする
商品の値上げを試みることで、売上アップに繋がります。同じ個数が売れた場合は当然ながら単価の高い方が総売上が高まりますので、無理に販売数を増やさなくてもよいメリットがあります。
デメリットとしては「客離れを誘発する」ことが挙げられるでしょう。商品購入の決め手を価格に置いている顧客が多い場合、客単価は上がっても販売個数が減ってしまうことも考えられます。
そうなると、総売上が減ってしまう可能性もあります。
販売数を増やす
販売数を増やすことで、売上アップに繋がります。売上は「商品価格✕個数」で計算するため、個数を上げることで売上を向上させることができます。
販売数を増やすメリットとしては、施策が立てやすい点が挙げられるでしょう。より多くの人に買ってもらうために「広告を打つ」「販促プロモーションを行う」などが考えられます。
デメリットとしては、「広く認知されないと難しい」点でしょうか。商品にもよりますが、一般的に多くの販売個数を達成するためには多くの顧客が必要になります。
客単価を上げる
客単価を上げることも、売上アップに繋がるでしょう。一人の顧客が購入する量や価格を上げることで、顧客数や販売個数を増やさなくても売上向上が期待できるのがメリットです。
対して、「実現が難しい」点がデメリットとして挙げられます。客単価を上げるためには「一人が購入する個数を増やす」や「バリエーションを増やす」などが求められますが、どれも一朝一夕にはいかない問題です。
コストを下げる
利益をアップさせるには、コストを下げるのも有効です。コストを下げるには、下記のような方法が考えられるでしょう。
原価を下げる
原価を下げることでコストが下がり、結果として利益が向上します。原価を下げるメリットとしては「一度下げられれば長期的に効果が継続する」「原価率が高い場合は少ない努力で大きな成果が見込める」などが挙げられるでしょう。
対してデメリットしては「品質が粗悪になる可能性がある」「取引業者の信頼性を担保できない場合もある」といったところでしょうか。価格が安いものはどうしても品質が悪くなる傾向があるため、適性バランスを見極めることが重要です。
かかる費用を減らす
事業にまつわる費用を減らすことで、利益アップに繋がります。費用を下げるメリットとしては「工夫次第で成果が出やすい」「無駄を省くことで生産性もアップする」などが挙げられるでしょう。
対して、デメリットとしては「必要な費用まで削減すると売上が下がる」あたりが考えられます。「何を削って何を残すか」の判断に、根幹的な軸が必要です。
利益を上げる際に注意したいポイント

では次に、利益アップを考える際に注意したいポイントを解説します。利益向上を目的とする場合においても、見失ってはいけないファクターがあります。
必要な投資はしっかりと行う
利益はおおまかに「売上ーコスト」で求めることができます。そのため、前述の通りコストを削れば削るほど利益の増大が見込めるでしょう。
しかし、コストには「削るべきコスト」と「そうでないコスト」が存在します。前者は「売上に繋がらないコスト」「別の方法でカットできるコスト」であり、後者は「売上に繋がるコスト」「削ることでパフォーマンスが低下するコスト」です。
削らない方がよいコストとしては、一般的に下記のようなものが挙げられるでしょう。
- 広告宣伝費
- 採用費
- 設備投資費
もちろん企業が置かれている状況にもよるのですが、これらは将来的な売上をアップさせてくれるコストです。ビジネスが「先に投資をしてそれを上回るリターンを得る」行為である以上、ある程度の費用がかかってくることは避けられません。
ビジネスの肝を見極める
ビジネスの肝を見極めることで、正しい売上アップ手法を模索することができます。ビジネスの肝とは、要するに「自社の強み」です。自社がどのような環境に置かれ、何を強みとしてシェアを得ているのかをしっかりと分析しましょう。
そこが明確になれば、強みを強化し、さらなる売上アップが見込めます。ビジネスを伸ばす上では「弱みの克服」より「強みの強化」の方が有益と言われていますので、そのセオリーに従うのが無難です。
しかし、場合によっては弱みを克服した方が利益に繋がるケースもあるでしょう。その辺りを正しく見極めるためにも、自社ビジネスの肝を知ることが大事です。
システムを活用する
システムを活用することで、利益アップに繋がります。現代はテクノロジーの進歩により、さまざまな業務システムが開発・リリースされるようになりました。
自社のニーズに合ったシステムを導入できれば、大幅な業務効率化や生産性アップが見込めるでしょう。従来では取得するのが難しかった細かいデータに基づき経営判断を行ったり、手作業で行っていた処理を機械で自動化するなどの活用が考えられます。
業務にITを活用するのが当たり前と言える時代ですが、それだけにシステムが担う業務成果は多岐に渡ります。今後、より一層増大することが予想されるのではないでしょうか。
システムを導入することによるメリット
では次に、システムを導入することによるメリットについて考えたいと思います。システムを導入すれば、業務に下記のような恩恵が加わるでしょう。
業務が効率化されコストカットに繋がる
システムを導入すれば、業務が効率化されコストカットに繋がります。機械に任せられるような定型的な業務をシステムで自動化すれば、その分人的リソースを他の部分に回せ、業務時間削減が見込めます。
テクノロジーが進化したとはいえ、まだまだ人の手が必要な業務は存在します。機械に任せられるような定型的な業務に人的リソースを割いてしまうと、業務から柔軟性が欠けてしまうことにも繋がるでしょう。
そうなると、顧客満足度や売上が下がってしまい、利益のアップが難しくなってしまいます。
顧客のニーズに合わせたきめ細やかな対応ができる
システムを活用すれば、顧客のニーズに合わせたきめ細やかな対応が可能です。従来でも顧客一人一人のニーズに合わせた対応は可能でしたが、あくまで「顧客が求めているものを提供する」というレベルでした。
システムを使えば、顧客の潜在的なニーズを各種データから予測することができます。それに基づいて適切なタイミングでアプローチすれば、売上単価の向上や顧客満足度アップに繋げられるでしょう。
また、顧客の購買意欲をベースにグループ分けを行い、それぞれに異なる対応をすることも可能です。例えば、購買意欲が十分に温まっている見込み客は営業担当者に渡し商談、そうでない顧客はメルマガやオウンドメディアを介して啓蒙、といった具合です。
利益を上げるにはどのようなシステムを使えばいいか

利益を上げるためには、どのようなシステムを使えばよいのでしょうか。最後に、利益アップに繋がるシステムをご紹介します。
CRM
CRMはCustomer Relationship Managementの略であり、日本語では「顧客管理システム」と呼ばれています。CRMを導入することで顧客との関係を適切に管理し、顧客満足度や売上のアップが見込めます。
具体的には「顧客情報管理」や「プロモーション管理」、「データ収集・分析機能」などが搭載されています。関係のある顧客情報を集約的に管理し担当者以外の従業員でも顧客情報を参照できるようにすることで、対応を平準化できます。
また、プロモーション管理やデータ分析により、顧客一人ひとりに合ったアプローチを行えるでしょう。
SFA
SFAのはSales Force Automationの略であり、日本語では「営業支援システム」と呼ばれています。営業活動におけるプロセスを可視化し管理することで、営業効率をアップさせるためのシステムです。
具体的には「案件管理」や「売上予測」「予実管理」といった機能が搭載されています。各担当者が抱えている案件をシステムで管理することにより、マネージャーがひと目で状況を把握・判断できるようになるでしょう。
また、売上予測や予実管理を活用すれば、目標に対する進捗や管理が容易になります。
MA
MAはマーケティングオートメーションの略であり、その名の通りマーケティング業務を自動化してくれるシステムです。マーケティングオートメーションを導入すれば、従来のマーケティングプロセスを効率化でき、成約率アップに繋がるでしょう。
具体的には、「スコアリング」や「メルマガ配信」、「リード管理」などの機能が備わっています。自社が獲得したリードを適切に管理し、熱量によって異なったアプローチを行い、最終的に営業担当者に渡して成約に繋げるといった使い方が一般的です。
まとめ
利益は「売上ーコスト」で求められるため、利益アップには「売上を上げる」「コストを下げる」といったやり方が有効です。そのための強い味方となるシステムについてしっかりと学び、業務生産性の向上に繋げましょう。

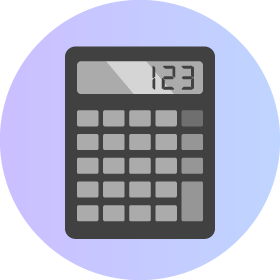
Microsoftを導入して
コスト効率をよくしたい

Microsoftに関して
気軽に聞ける相談相手が欲しい

Microsoftを導入したが、うまく活用できていない・浸透していない

社内研修を行いたいが
社内に適任者がいない
Bizwindでは、Microsoft導入支援事業などを中心に
IT・DX推進に関する様々なご相談を承っております。
ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。